社会福祉における自己と他者の理解
〜真の支援関係を築くための基盤〜
社会福祉の現場では、自己理解と他者理解が支援の成否を左右する重要な要素となります。支援者として、私たちはどのように自分自身と向き合い、利用者との関係を構築していけば良いのでしょうか。
1. 自己理解の重要性
社会福祉実践において、自己覚知は支援者の基本的な資質として位置づけられています。自分自身の価値観、偏見、感情的な反応パターンを理解することで、利用者との関係において生じる逆転移やカウンタートランスファレンスを適切に扱うことができます。
支援者が自分のパーソナリティやアイデンティティを深く理解していない場合、無意識のうちに利用者に自分の価値観を押し付けたり、適切なバウンダリーを保てなくなる危険性があります。これは支援関係の質を著しく低下させる要因となります。
💡 実例:高齢者施設での事例
A職員は、自分の祖母との関係から「高齢者は保護されるべき存在」という固定観念を持っていました。しかし、リフレクションを通じて自己の価値観を見つめ直し、利用者の自立性を尊重する支援へと変化しました。
2. 他者理解への道筋
エンパシー(共感的理解)は他者理解の核心的な能力です。利用者の立場に立って物事を捉え、その人の経験世界を理解することで、より効果的な支援が可能になります。しかし、これは単なる同情や感情移入とは異なります。
カール・ロジャースが提唱した無条件の積極的関心は、他者理解における重要な概念です。利用者を一人の人間として尊重し、その人のストレングス(強み)に注目することで、支援関係における信頼関係が構築されるのです。
3. 支援関係における相互作用
社会福祉実践では、支援者と利用者の間に相互作用的な関係が成立します。この関係性において、両者が互いに影響を与え合いながら成長していくプロセスが重要です。
システム理論の観点から見ると、支援者と利用者は一つの相互作用システムを形成します。このシステム内でのフィードバックやコミュニケーションの質が、支援の成果を大きく左右します。
4. 実践的なアプローチ
スーパービジョンの活用
定期的なスーパービジョンを通じて、自己理解を深めるとともに、事例検討を行うことで他者理解のスキルを向上させることができます。
ナラティブ・アプローチ
利用者の人生の物語を聞き、その中に含まれる意味や価値を理解することで、その人らしい支援計画を立てることが可能になります。
5. 課題と展望
現代社会における多様性の拡大に伴い、支援者には文化的感受性やインターセクショナリティへの理解が求められています。異なる背景を持つ利用者との関係構築においては、従来の枠組みを超えたアプローチが必要です。
また、デジタル技術の発展により、オンラインでの支援提供も増加しており、対面とは異なるラポール形成の技術が求められています。
📖 参考文献・論文
・秋元美世(2021)『社会福祉学の基本視座』有斐閣
・山縣文治・柏女霊峰編(2020)『社会福祉用語辞典 第10版』ミネルヴァ書房
・田中英樹(2022)「社会福祉実践におけるリフレクションの意義」『社会福祉学』63(2), pp.15-28
・佐藤久夫(2021)「多文化共生社会における福祉実践の課題」『ソーシャルワーク研究』47(3), pp.45-52
・全国社会福祉協議会(2023)『地域福祉実践事例集』
・日本ソーシャルワーカー協会(2022)『実践報告書:多様性に対応する支援の在り方』


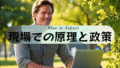
コメント