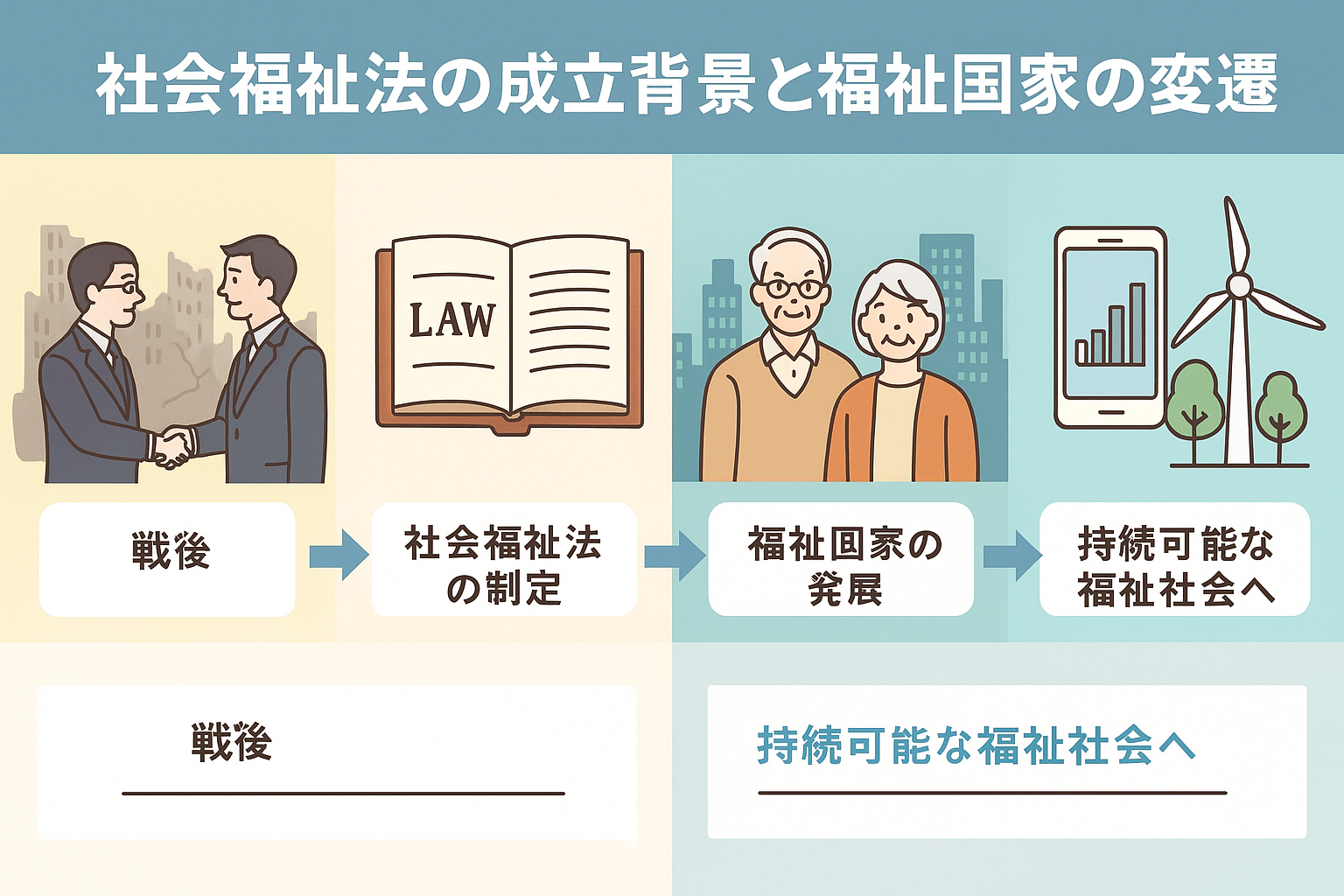
- 戦後日本における社会福祉法の成立背景
- 福祉三法から福祉国家への歩み
- 高度経済成長と福祉制度の拡充
- 現代の課題と福祉国家の展望
- 次回予告:社会福祉法の課題と展望
戦後日本における社会福祉法の成立背景
戦後の日本は、国民の最低限度の生活を保障するため、社会福祉制度の整備が急務となりました。1947年、日本国憲法第25条が制定され、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明記されました。この理念を具体化するため、社会福祉法の前身である社会福祉事業法が1951年に制定されました。
福祉三法から福祉国家への歩み
1950年代から1960年代にかけて、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法のいわゆる福祉三法が制定され、福祉制度の基盤が築かれました。これらの法律は、国民の生活を支えるための重要な柱となりました。
高度経済成長と福祉制度の拡充
1960年代から1970年代にかけての高度経済成長期には、国民皆保険・皆年金制度が実現し、福祉制度が大きく拡充されました。1973年は「福祉元年」と呼ばれ、福祉予算の大幅な増加やサービスの拡充が図られました。
現代の課題と福祉国家の展望
現代の日本は、少子高齢化や福祉人材の不足など、さまざまな課題に直面しています。これらの課題に対応するため、地域福祉の強化やICTの活用など、新たな取り組みが求められています。
次回予告
次回は「社会福祉法の課題と展望」について、現代の福祉制度が抱える問題点と今後の方向性を詳しく解説します。
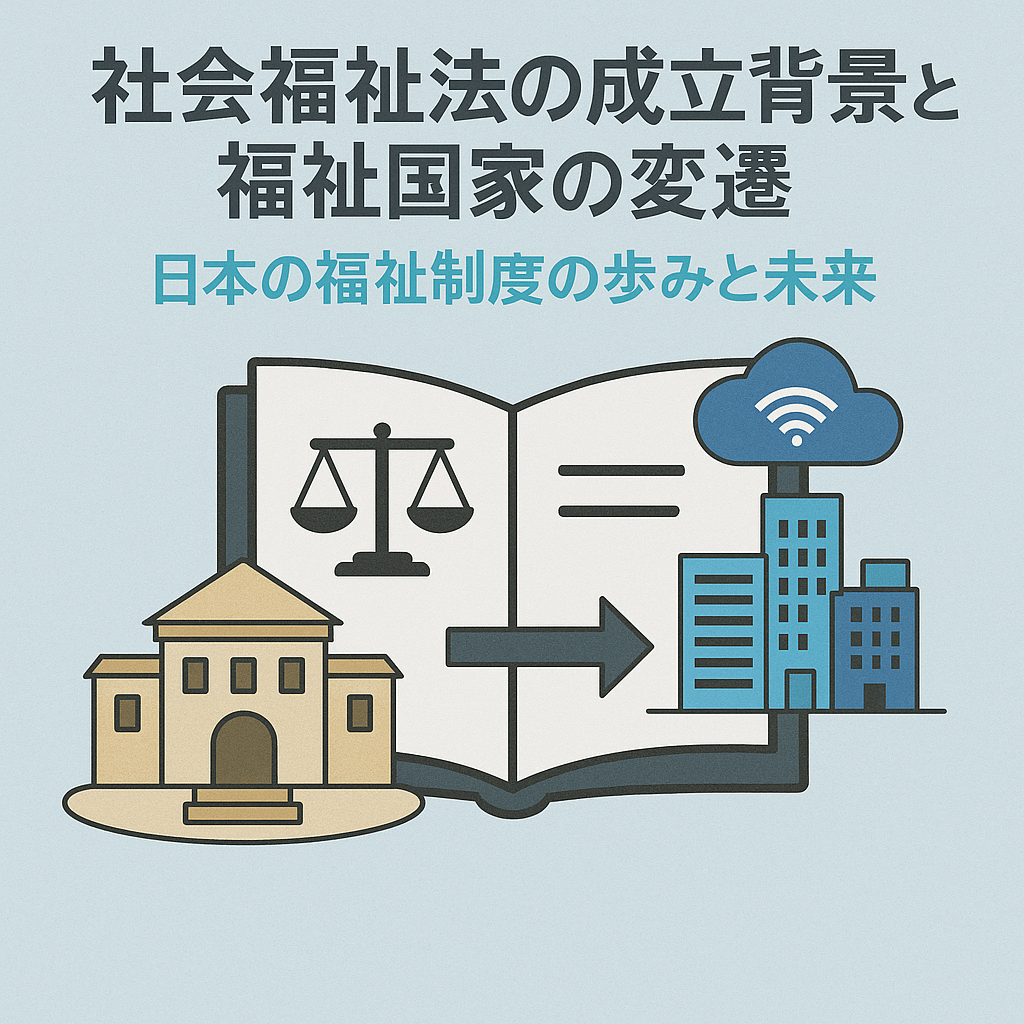


コメント